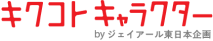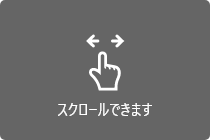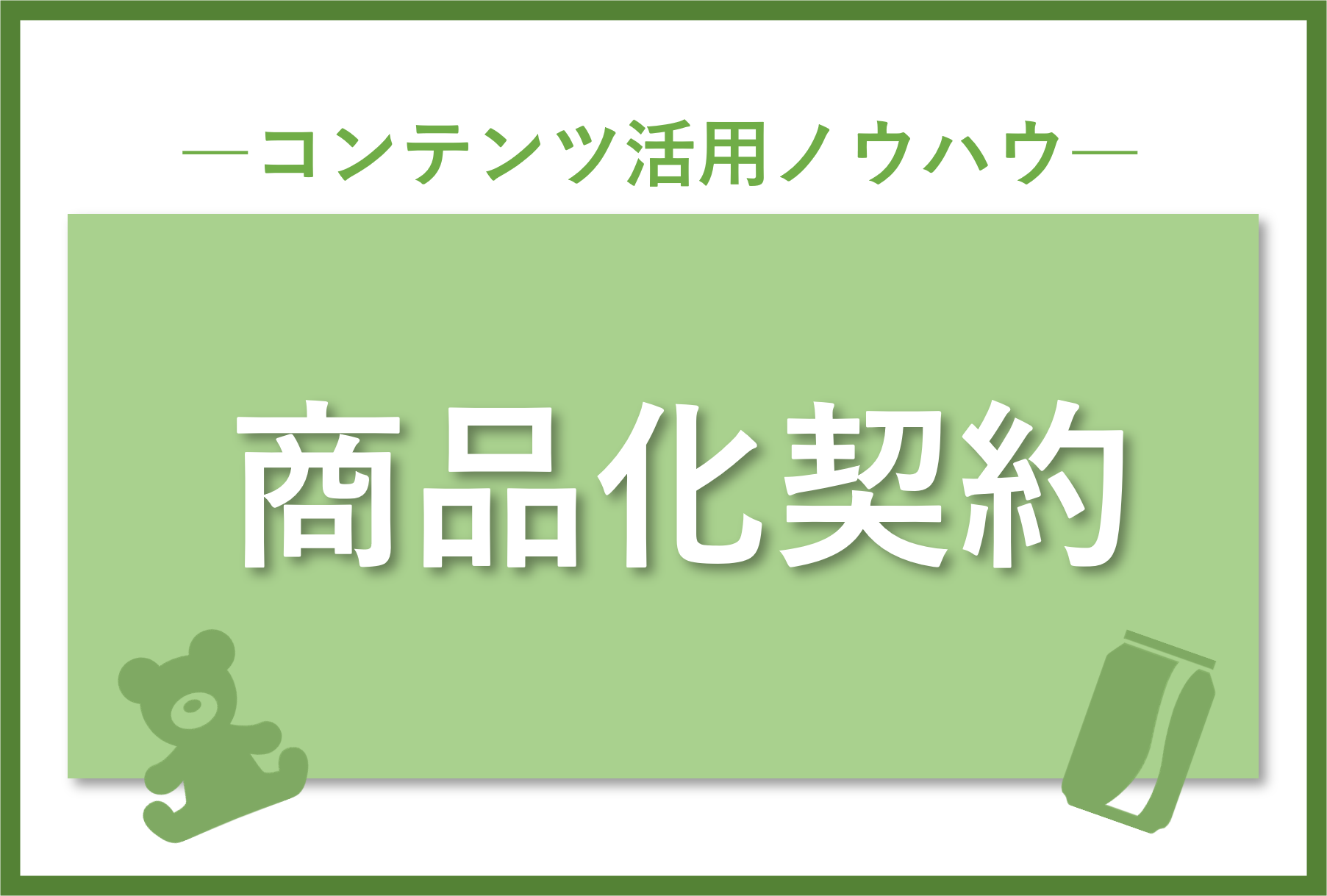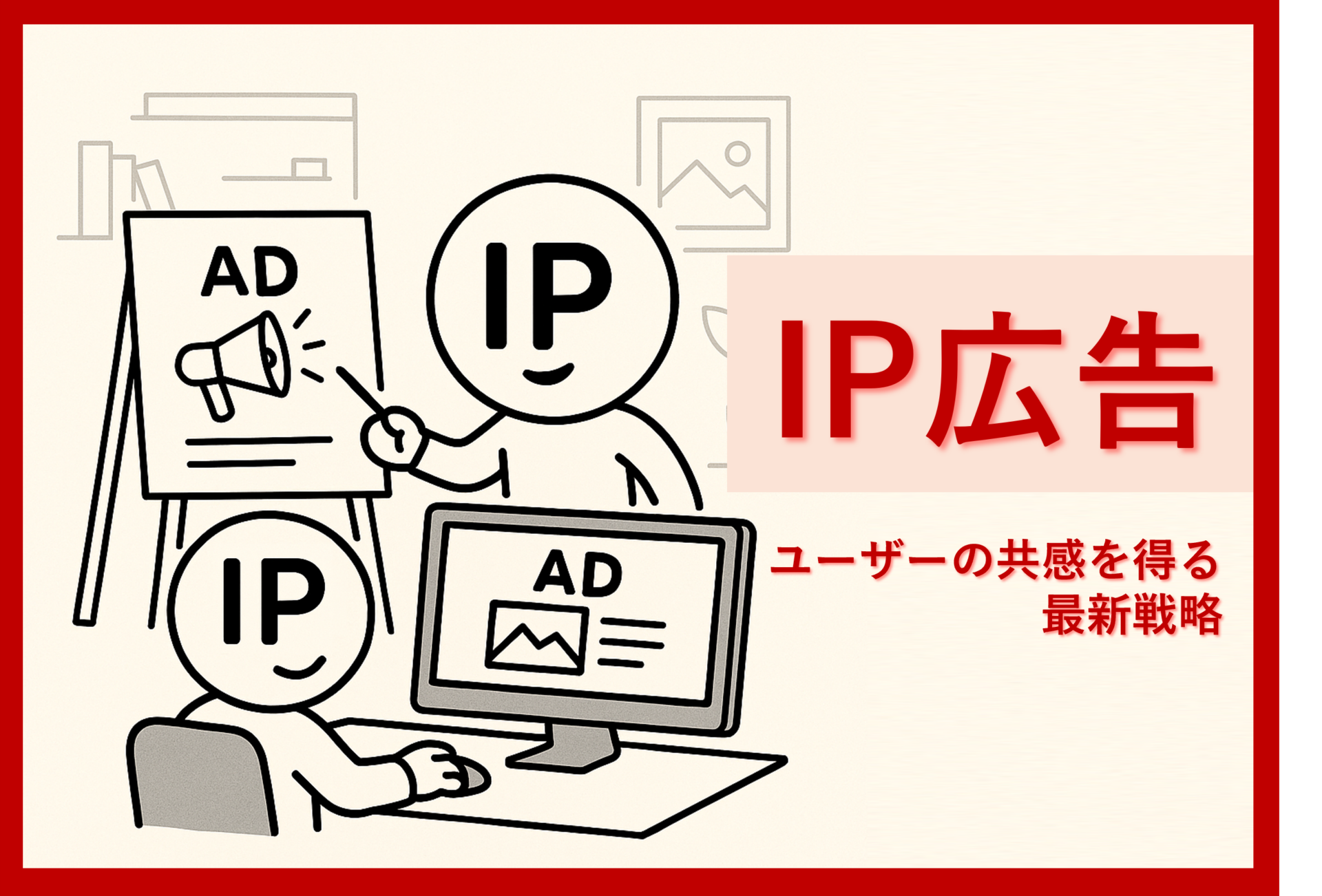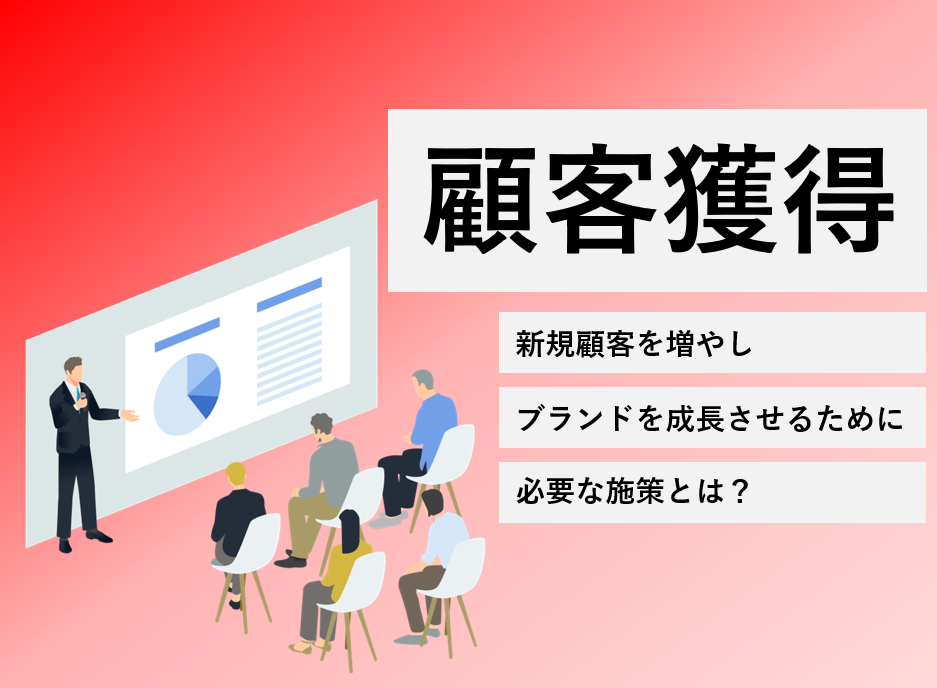こんにちは、ジェイアール東日本企画「キクコト」編集部です。
「企業SNSのフォロワーがなかなか増えない」
「キャンペーンをやったのに、終わった途端フォロワーが減ってしまった……」
そんな悩みはありませんか?
SNSキャンペーンは、認知拡大やファン獲得に効果的なマーケティング施策のひとつですが、やみくもに企画しても継続的な成果は得られません。このコラムでは、SNSキャンペーンを成功させるためのポイントから、注意すべき点まで、成功事例とともに詳しく解説します。
企業のSNSフォロワーを増やし、アカウントを育てていくためのヒントを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
SNSキャンペーンとは
SNSキャンペーンとは、企業がX(旧Twitter)やInstagram、LINE、TikTokなどのソーシャルメディアを活用して行う販促やブランディングの施策です。
特定の投稿に「いいね」や「リポスト(再投稿)」をしてもらったり、ハッシュタグを付けて写真を投稿してもらったりすることで、ユーザーの参加を促しながら、認知度の向上やファン育成につなげることが特徴です。
たとえば、以下のような施策が代表的なSNSキャンペーンの例です。
【例】
・フォロー&リポスト(またはコメント)で応募できるプレゼント企画
・ハッシュタグ+写真投稿で参加するフォトコンテスト
・キャンペーン音源を使った動画投稿キャンペーン
特に近年では、SNSのアルゴリズムの変化や購買行動の多様化により、企業からの一方的な情報発信よりも、ユーザーによるコメントや投稿を促し、エンゲージメントを高めるタイプのSNSキャンペーンが注目されています。
SNSキャンペーンのメリット
SNSキャンペーンというと、「とにかくフォロワー数を増やすための施策」と思われがちですが、重要なのはブランドに共感し、自発的にアクションを起こしてくれるユーザーを増やすことです。
■高い拡散力による認知拡大
SNSキャンペーンの最大の強みは、効率よく広範囲にリーチできる点です。
たとえば、X(旧Twitter)でフォロー&リポスト企画を実施すると、ユーザーによるリポストを通じて自然な形で情報が二次拡散し、広告では届きにくい層にもアプローチできる可能性が生まれます。
ただし、ユーザーが「参加したい」「ほかの人にも共有したい」と思える内容でなければ、大きな成果は期待できません。
■フォロワーやファンとのエンゲージメントが深まる
キャンペーンをきっかけにフォロワーとの対話や参加を促すことで、ブランドに対する親近感が高まり、関係性がより深まる点も大きな魅力のひとつです。
たとえば、「#◯◯のある生活」や「#私の推しメニュー」といった共感を得やすいテーマの投稿キャンペーンは、フォロワーにとってブランドを“自分ごと”として捉えるきっかけとなり、消費者からブランドや商品のファンに育つ一歩となります。
さらに、SNSのアルゴリズム上、「いいね」やコメントを頻繁に行うアカウントは、ユーザーのホーム画面に表示されやすくなる傾向があります。そのため、キャンペーンでエンゲージメントが高まると、日常的な情報発信もユーザーの目に留まりやすくなるというメリットもあります。
■ユーザー生成コンテンツ(UGC)が、ブランディングにつながる
ハッシュタグ付きの投稿キャンペーンなどを実施することで、ユーザー自身が自発的にブランドや商品を紹介するコンテンツ(UGC:User Generated Content)を生み出せます。
UGCには、以下のような利点があります:
・ユーザー目線でのリアルな口コミ効果がある
・広告らしさがなく、信頼性・共感性が高い
・自社アカウントや広告素材に二次利用できる
企業が発信する広告などの一次情報だけでなく、SNSで他のユーザーからの評価を確認する人が増え、ユーザー目線の投稿(UGC)が購買行動に与える影響はいっそう大きくなっています。
■効果測定がしやすく、PDCAを回しやすい
SNSキャンペーンは、数値としての反応が可視化されやすい点もメリットです。
たとえば、以下のような指標が活用できます:
・投稿のインプレッション数
・エンゲージメント率(いいね・コメント・リポスト)
・ハッシュタグ投稿数
・キャンペーン参加数、フォロワー増加数
こうしたKPIを設計しやすいため、キャンペーンを通じて「何が響いたのか」「改善すべき点は何か」を明確にし、次の施策へ活かしやすいという強みがあります。
以上のようなメリットを活かすことで、SNSキャンペーンは認知度向上や企業・ブランドファンの獲得につながる、非常に重要な施策です。
企業のSNSキャンペーン成功事例 8選
事例①【フォロワー増加・維持】インスタントウィンキャンペーン|ローソン
ローソンでは、キャンペーン応募後にすぐ当選結果がわかる形式の「インスタントウィンキャンペーン」をX(旧Twitter)で定期的に実施しています。
すぐに結果がわかるキャンペーンは、参加のハードルが低く、ユーザーが増えやすいのが特徴です。キャンペーンを定期的に実施することでフォロワーの離脱を防げますが、キャンペーン目当てでターゲット外のフォロワーが増えてしまうことがあります。
そのため、金券のように誰もが欲しがるプレゼントは避け、ターゲット層が欲しがる景品をプレゼントするようにしましょう。
事例②【口コミを増やす】#推しド総選挙2023|ミスタードーナツ
ミスタードーナツは、X(旧Twitter)と公式サイトで、自社商品の総選挙「#推しド総選挙2023」を実施しました。
Xでは、「#推しド総選挙2023」と好きなドーナツのチームのハッシュタグをつけて投稿することで選挙に参加でき、さらに抽選でギフトチケットが当たるキャンペーンです。
「選挙」や「推し」といったキーワードを用いることで、
・好きなドーナツを応援するファン同士に一体感が生まれた
・ドーナツへの感想や好きなポイントの投稿が増えた
といった成果を生み出し、ブランディングにつながるキャンペーンになりました。
事例③【ブランディング】#ヨックモックってどんな味キャンペーン|ヨックモック

引用:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000303.000012005.html
洋菓子ブランド・ヨックモックは、設立55周年を記念して、「#ヨックモックってどんな味」のハッシュタグを用いた投稿キャンペーンをX(旧Twitter)上で実施しました。
誰もが一度は食べたことのあるヨックモックとの“思い出”をユーザーに投稿してもらうキャンペーンで、周年ならではの懐かしさと親しみを活かしながら、ブランドとユーザーの関係を再確認するブランディング施策となりました。
メイン顧客層が50~70代という中で、課題であった若年層へのアプローチとして、Z世代から支持の高い人気イラストレーターを起用。新たな視点で表現されたアニメーションは、公開と同時にSNS上でも多くの関心を集めました。
その結果、約1万件にのぼる投稿が集まり、アニメーションも「思い出がよみがえる」と話題に。ブランドの持つ“記憶に残るおいしさ”という価値を改めて訴求しながら、世代を超えたブランディングに成功しています。
■参考:https://www.advertimes.com/20250703/article504131/
事例④【エンゲージメントを上げる】TikTok踊ってみたキャンペーン|キユーピー
キユーピーでは、TikTokでテレビ番組「キユーピー3分クッキング」でおなじみのテーマ曲を使用し、ダンス動画の投稿キャンペーンを実施しました。
ハッシュタグ「#キユーピー3分クッキング踊ってみた」をつけたダンス動画を投稿すると、選ばれた動画が番組のオープニングで放映され、さらにキユーピー商品とオリジナルグッズの詰め合わせセットがプレゼントされるキャンペーンです。
「番組のオープニングで自分の動画が流れる」という体験が魅力となり、多くのユーザーが参加しました。このような音源を使ったダンスキャンペーンは、参加したユーザーの記憶に残りやすく、ファンとのエンゲージメントを強める効果があります。
事例⑤【参加・シェアしたくなる】診断型キャンペーン|湖池屋
湖池屋は、X(旧Twitter)上で「#ピュアポテト診断」を実施し、診断結果をシェアすると商品詰め合わせが抽選で当たるキャンペーンを展開しました。
このような診断型や占い型のキャンペーンは、エンタメ性が高く、ユーザーが結果を共有したくなる心理を自然に喚起できる点が特徴です。診断コンテンツに参加する過程でそのままキャンペーン応募まで完了するため、参加のハードルが低く、拡散性にも優れています。
また、本キャンペーンでは外部サイトを使用せず、X上のみで完結する構成となっており、ユーザーが手軽に参加できた点も、離脱者が少なく、多くの反応を集めたポイントです。
事例⑥【UGCを生み出す】ARカメラ+写真投稿キャンペーン|花王 メリーズ
花王 メリーズは、おむつの写真や動画とともに購入商品の感想を「#メリーズ」のハッシュタグ付きで投稿することで、賞品と企業キャラクターのぬいぐるみなどが当たるキャンペーンをInstagram上で実施しました。
このキャンペーンでは、投稿のきっかけとしておむつのパッケージ風の写真が撮れる「ARカメラ」を活用しています。ARカメラで撮影すると、まるで“わが子がおむつモデルデビューしたかのような体験”ができる仕様になっています。これにより、楽しい撮影体験とシェア意欲を自然に引き出すことに成功しています。
おむつのように、同じユーザーの継続購入が難しい商材においても、定期的な写真投稿キャンペーンを実施することでUGC(ユーザー生成コンテンツ)を創出し、自然な形で口コミが広がる仕組みを構築しています。
また、花王 メリーズのInstagramアカウントでは、実際のユーザー投稿(UGC)を多数活用して定期的な更新を行っており、フォロワーとのエンゲージメント維持にもつながっています。
事例⑦【接点強化】LINEスタンププレゼント|第一生命
第一生命のデジタル完結型保険ブランド「デジホ」は、公式LINEアカウントを友だち追加すると、Z世代に人気のキャラクター「ちみたん」とのコラボLINEスタンプがもらえるキャンペーンを実施しました。
この取り組みは、スマホ医療保険のターゲット層である若年層との接点を強化することを目的としたもので、気軽に参加できるLINEスタンプキャンペーンを通じて、ブランドとの接触機会を増やしています。
LINEは、他のSNSと比べて日常的に使われる頻度が高く、アクティブユーザー数も非常に多いため、広いターゲットを狙うのにおすすめです。さらに、公式LINEは登録したユーザーへクローズドな情報を直接届けられるようになるため、購入ハードルの高い保険商品においても親和性の高いSNSです。
事例⑧【参加型で話題化】アニメ「推しの子」コラボキャンペーン|ホットペッパービューティー

引用:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002070.000011414.html
ホットペッパービューティーは、人気アニメ「推しの子」とコラボし、キャラクター3人のCM用ヘアスタイルをファンの投票で決定する参加型キャンペーンを実施しました。
投票は専用ページから行う形式で、投票完了後にX(旧Twitter)でシェアすると、全員にオリジナルイラストがプレゼントされる仕組みとなっており、ファンのエンゲージメントを高める設計がされています。
このキャンペーンでは、最終的に18万4,125票という大規模な投票数を獲得しました。さらに、ファンの投票によって選ばれた髪型が実際にCMに採用されることで話題性が生まれ、SNSを中心に大きな反響を呼びました。
ホットペッパービューティーでは本施策に限らず、「ブルーロック」「忍たま乱太郎」など、若年層に人気のアニメ作品とコラボした“髪型チェンジキャンペーン”を継続的に実施しており、アニメファンからの支持を着実に獲得しています。
SNSキャンペーンを成功させるためのポイント
成功事例として挙げたSNSキャンペーンはどれも単なる「プレゼント企画」にとどまらず、ユーザーの共感や、拡散・参加を上手に促しています。SNSキャンペーンを成功させるには、ユーザーに届く設計が何よりも重要です。事例を参考に成功のポイントを4つ紹介します。
1. キャンペーンの目的を明確にする
まず、「このキャンペーンは何のために実施するのか?」という目的を明確にすることが必要です。
【例】
・認知拡大(例:新商品やブランドの周知)
・購買促進(例:クーポン配布やECサイト誘導)
・ファンの育成(例:UGCによるブランド愛着づくり)
「なんとなく話題化したい」「とりあえずフォロワーを増やしたい」といったあいまいなゴールで始めると、成果を得ることが難しくなるため、しっかりとした設計が重要です。
「認知拡大のために期間中に5000リポストされる」「UGCの投稿を1000件達成」など、測定可能な数値目標(KPI)を設定すると、振り返りがしやすくおすすめです。
2. ターゲットをデータで明確にする
次に大事なのが、「誰に向けてキャンペーンを行うか?」というターゲットの明確化です。よくある失敗として、「全員に刺さる内容を」と考えてしまい、結果的に盛り上がらなかったり、キャンペーン終了後にフォロワー数が減ってしまうことがあります。
SNSキャンペーンは、「共感」や「自分ごと化」することで参加率が高まります。ターゲットに合わせて、キャンペーンの見せ方やプレゼントの内容を選ぶことが重要です。
以下の3つをもとにターゲットを設定しましょう。
① 自社のターゲットとなるペルソナの設計
② SNSごとのユーザー層の理解
③ 自社SNSアカウントのアナリティクスを確認
①自社のターゲットとなるペルソナの設計
キャンペーンの目的に合わせて、ペルソナ像を具現化しておくと企画がぶれにくくなります。たとえば、単に「20代女性」ではなく、「一人暮らしのOLで、毎朝Instagramでお弁当の写真をストーリーズにアップする女性」と具体的にイメージしたほうが、キャンペーンの参加ハードルをユーザー目線で考えやすくなります。
ペルソナの設定の仕方は、こちらの記事でさらに詳しく紹介しています。
②SNSごとのユーザー層の理解
各SNSごとに使われ方・ユーザー属性・拡散構造が異なることを把握しておきましょう。そのうえで、キャンペーンの目的(認知・販促・ファン化)やターゲットに合ったSNSを選択しましょう。
| SNS | ユーザー層 | 主な特徴 | 向いているキャンペーン例 |
| X(旧Twitter) | 10~20代を中心に幅広い | 拡散力が強く、リアルタイム性が高い | フォロー&リポスト、エピソード投稿キャンペーン、診断・占いキャンペーン |
| 10~30代の女性 | 写真投稿に強く、ビジュアル重視 | ハッシュタグでの写真・動画投稿キャンペーン | |
| TikTok | 若年層、特に10代 | フォロー外のユーザーへリーチしやすい | ダンス・チャレンジ系投稿キャンペーン |
| LINE | 若年層からシニアまで幅広い層が利用 | 1対1で情報を提供できる/通知力が高い | クーポン配布、スタンププレゼント、リピーター向け施策 |
| 30~40代 | 実名登録制で情報の信頼度が高い | コメントキャンペーン、ハッシュタグ投稿キャンペーン |
③自社SNSアカウントのアナリティクスを確認
現在の自社SNSアカウントのアナリティクスを確認し、どのようなフォロワーが多いかを把握することも重要です。現在のフォロワー層に合わないキャンペーンを実施すると、ローンチ時にキャンペーンが伸びにくくなったり、かえってフォロワーが減ってしまう可能性もあります。
たとえば、「20代女性のフォロワーが多く、平日20時以降の投稿に最も反応がある」ことがわかれば、それに合わせて投稿内容や時間を調整することで、フォロワーによってキャンペーンが拡散されやすくなります。
3. 参加したくなる仕掛け・コンセプト
SNS上には多くのキャンペーンがあふれています。その中で、「このキャンペーンに参加したい」となる動機づけが重要です。上述した事例を参考に、参加したくなる仕掛けを紹介します。
● 簡単に参加できる
「簡単に参加できてお得」とユーザーに思わせることが大切です。
【事例】
→ ローソンのすぐに結果がわかるインスタントウィンキャンペーン
→ 第一生命の公式アカウントをフォローするだけでもらえるスタンプキャンペーン
→湖池屋のXだけで完結する診断キャンペーン
● 共感・応援したくなるストーリー
SNSは自ら発信する場であるため、ユーザーに「発信したい」と思わせるストーリーが重要です。
【事例】
→ ミスタードーナツの、推しドーナツを応援する「#推しド総選挙2023」
→エピソードトークを募集する「#ヨックモックってどんな味キャンペーン」
● ここでしか得られない体験
キャンペーンに参加することでしか得られない体験を提供すれば、参加ハードルが高くても参加意欲を高められます。
【事例】
→ キユーピーの「踊ってみた」キャンペーン:番組のオープニングに採用される
→ メリーズのARカメラ:自分の子どもがモデルになったような体験ができる
● キャラクターとのコラボ
人気キャラクターとのコラボにより、そのキャラクターのファン層がキャンペーンに参加してくれ話題になります。
【事例】
→ 第一生命のコラボスタンププレゼント
→ ホットペッパービューティと「推しの子」のコラボ
キャラクターとのコラボはファンによる拡散が期待でき、SNSキャンペーンと特に相性が良い施策です。
キャラクターを活用した広告・プロモーションのメリット、契約の種類、施策の進め方までをわかりやすく解説した「キャラ活はじめてガイド」も公開中です。キャラクター起用に興味のある方は、ぜひご活用ください。
4行動を引き出すビジュアル設計
SNSでは、ユーザーは投稿をじっくり読む前にまず“ぱっと見の印象”で興味の有無を判断します。そのため、キャンペーン投稿の画像や動画は、直感的に内容が伝わるように設計することが重要です。
デザインのポイント
● 「キャンペーンであること」「参加方法」「プレゼント内容」が1枚目の画像でわかるようにする
→ 「キャンペーン実施中!」「#〇〇で投稿しよう!」などのコピーを大きく明記する、プレゼントは画像で掲載する など
● 文字情報は多くなりすぎないようにまとめる
→ スマホでの閲覧が中心となるため、文字サイズに注意し、読みやすさを意識しましょう。
1枚に無理に情報を詰め込まず、カルーセル(複数枚投稿)を活用すると伝わりやすくなります。
また、情報過多になると視認性が落ち、参加ハードルが上がるリスクもあるため、規約や詳細情報は別ページ(キャンペーンページなど)にまとめるのがおすすめです。
● 参加方法はシンプルに伝える
→ 投稿手順をイラストで示す、投稿例の画像を掲載するなど、視覚的にわかりやすく工夫しましょう。
● ターゲットに合ったトンマナでデザインする
→ 例えば、女性がメインターゲットであればトレンド感のある柔らかい雰囲気に、ビジネスパーソン向けであればスマートで洗練された印象にするなど、ユーザーが“自分ごと”としてとらえやすいビジュアルを意識しましょう。
SNSキャンペーンを実施する際の注意点
SNSキャンペーンを設計する際は、アイデアや企画内容ばかりに目が向きがちですが、法令や各SNSのルールに違反すると、最悪の場合キャンペーン中止につながることもあります。ここでは、SNSキャンペーンを実施するうえで押さえておくべき「利用規約」と「景品表示法(景表法)」の基本ポイントをご紹介します。
各SNSプラットフォームの利用規約に注意する
SNSキャンペーンでは、X(旧Twitter)やInstagramなどのプラットフォームごとのルールを事前に確認し、遵守する必要があります。
X(旧Twitter)の注意点
Xのキャンペーンで特に気を付けるべきポイントは以下の3つです。
①「フォロー」「いいね」に対して直接報酬を設定しない
フォローやいいねの購入は禁止されているため、フォローで必ず景品を提供することはせず、必ず抽選で選ばれる仕組みにしましょう。
自身または他者のフォロワーやエンゲージメントを人為的に誇張することは禁じられています。これには以下の行為が該当します。
ツイートやアカウントの測定データの増加を販売または購入すること – フォロワーやエンゲージメント(リツイート、いいね、@ツイート、投票)を販売または購入すること
Xヘルプセンター プラットフォームの操作とスパムに関するポリシー
②複数アカウントでの同一キャンペーン応募の禁止を明記する
キャンペーンに応募するユーザーが当選確率を上げるために複数のアカウントでキャンペーンに応募することをXでは明確に禁止しています。キャンペーンの規約には「複数のアカウントで応募した利用者は当選資格を失うこと」を記載しましょう。
キャンペーンに何度も応募するために多くのアカウントを作った利用者は、すべてのアカウントが凍結されることになります。複数のアカウントで応募した利用者は当選資格を失うことを必ず明記してください。
Xヘルプセンター キャンペーンの実施についてのガイドライン
③繰り返し同じ内容のポストをさせない
同じポストを繰り返すことは、Xのルール違反となっています。そのため、ポストで応募するキャンペーンの場合は、「1アカウント1投稿のみ対象」にするなどユーザーに同じ投稿をさせない工夫をしましょう。
まったく同じ、またはほとんど同じ内容やリンクを投稿することはXルール違反であり、検索の品質を低下させる恐れがあります。同じポストを何度も繰り返すように推奨するルールは設定しないでください(「一番多くリポストした利用者に賞品を提供」など)。
Xヘルプセンター キャンペーンの実施についてのガイドライン
Instagramの注意点
以下の3点を踏まえるようにしましょう。
①「フォローでプレゼントが当たる!」などの表現は避け、あくまで応募条件にフォローが必要という書き方をする(当選発表にDMを使うためフォローが必要など)こと
②「フォロー&いいねで当たる」のような単純なキャンペーンではなく、投稿やコメントなどユーザーとのコミュニケーションを目的としたキャンペーンにすること
「いいね!」、フォロー、シェアを人為的に集めたり、同じコメントやコンテンツを繰り返し投稿したり、利用者の同意を得ずに商業目的で繰り返し連絡したりしないでください。スパムのない環境を維持しましょう。「いいね!」やフォロー、コメントを含むやり取りの見返りに、金銭や金券などのプレゼントを申し出たりしないでください。誤解を招く偽のユーザーレビューや評価の提供、勧誘、取引に関与したり、これらの行為を促進、奨励、助長、承認するようなコンテンツを投稿しないでください。
Instagramコミュニティガイドライン
③第三者の写真を使用することはNG
写真や動画は、自分で撮ったか、共有する権利を得ているもののみをシェアしてください。
Instagramコミュニティガイドライン
Instagramに投稿されたコンテンツは、投稿者の所有物です。偽りのないコンテンツを投稿することを心がけ、インターネットからコピーまたは入手した、あなた自身が投稿する権利を持っていないものは投稿しないでください。知的財産権について、詳しくはこちらをご覧ください。
UGCを利用する際は、投稿主から必ず許可を得るようにしましょう。
また、許可を得ていても同じ写真をそのまま使用すると、無断転載と誤解される可能性があります。投稿主と共同投稿の形式をとったり、オリジナルのフレームやキャンペーンロゴを入れて加工するなどの工夫を行いましょう。
共通の注意点
●プラットフォームが提供する「プロモーションポリシー」や「ヘルプセンター」の最新情報を確認する
●「不正なアカウントからのキャンペーン参加」や「アカウントのBAN(凍結)」を避けるため、参加のハードルを下げすぎないことも重要
他社も同様のキャンペーンを実施しているからといって、確認を怠るとアカウント停止のリスクがあります。XやInstagramなど大手SNSは、ガイドライン違反を犯したアカウントについて詳細な理由を説明しない場合があり、そうなると復旧対策は難しいケースが非常に多いです。
ガイドラインの内容が明確でない場合、他社の事例をうのみにせず、グレーゾーンにあたる可能性のあるキャンペーンは避けることが賢明です。
景品表示法(景表法)のルールを必ず守る
SNSキャンペーンを実施する際は、「景品表示法(景表法)」による規制にも注意が必要です。
景表法では、「不当表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」が定められており、特に景品額の制限について事前に確認することが重要です。
【キャンペーンを行う前に必ずチェック】
消費者庁 景品表示法関係ガイドライン
消費者庁 事例で分かる景表法
プレゼントが抽選で当たる一般的なSNSキャンペーンは、「オープン懸賞」または「一般懸賞」に該当します。
■オープン懸賞とは
誰でも応募できる懸賞で、応募時に「購入」や「来店」などの取引条件がない場合に該当します。
例:フォロー&いいねで参加できるキャンペーンなど。
➡この場合、景品やサービスの提供に金額の上限はありません
■一般懸賞とは
商品の購入やサービスの利用など「取引」が発生するキャンペーンが該当します(=クローズド懸賞の一種)。
【例】商品の使用写真を投稿するキャンペーン、イベント参加後に写真をアップするキャンペーンなど。
➡この場合、景品の金額に上限があります。
景品額の上限(取引価格に応じて異なる)
●取引価格が5,000円未満の場合:景品の上限は2,000円
●取引価格が5,000円以上の場合:景品の上限は取引価格の20倍まで(ただし10万円が上限)
●商品の購入ではなく「来店」のみが条件の場合:取引価格は原則100円扱い → 景品の上限は2,000円
※応募条件だけでなく、景品の受け取りが「店舗での来店引き渡し」となる場合も、来店を伴う取引とみなされるため一般懸賞のルールが適用されます。
「必ず当たる!」などの誤った表示を避けること、「抽選方法」「当選者数」「景品内容」などを特設ページやキャンペーン投稿内で明確に記載するようにしましょう。
また、商品の発送が必要なキャンペーンの場合は、個人情報の取り扱いについても気を付ける必要があります。個人情報の保護に関する法的要件を遵守し、プライバシーポリシーや応募規約内に、個人情報の取得・利用・保管・共有に関する記述を必ずしましょう。
まとめ
SNSキャンペーンは、単なるフォロワー獲得施策にとどまらず、認知拡大・ファン化・ブランド理解の促進など、多面的なマーケティング効果をもたらす強力な手段です。
ただ豪華なプレゼントキャンペーンを行えばよいのではなく、目的やターゲットに応じたキャンペーンを設計することが非常に重要です。ご紹介した成功事例を参考に、ブランドらしいストーリーやキャラクターコラボなどのフックを作り、ユーザーが参加したくなるような魅力的なキャンペーンを実施しましょう。
当社、ジェイアール東日本企画では、SNSキャンペーンはもちろんのこと、多数のクライアントのプロモーションをサポートしてきました。課題解決のためのマーケティング戦略からご提案可能ですので、お気軽にご相談ください。
★SNSキャンペーン以外の販促施策についてさらに知りたい方は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。